テレビの正しい処分方法完全ガイド:家電リサイクル法に基づく6つの選択肢と費用相場
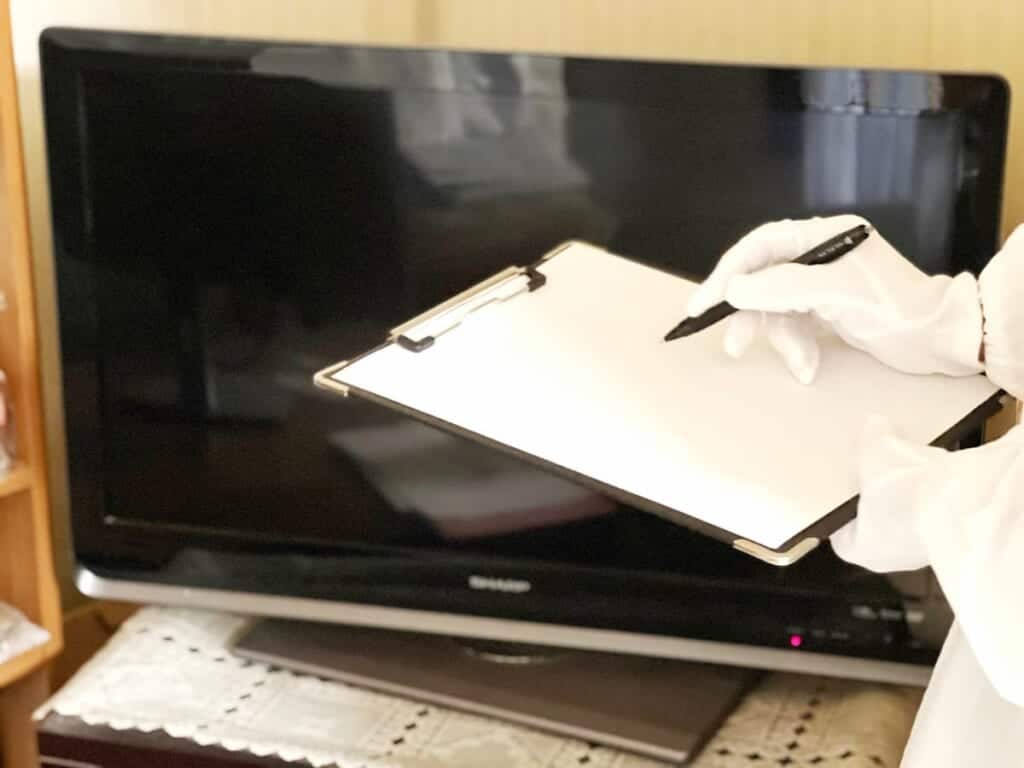
テレビを処分したいけど方法がわからない?本記事では、家電リサイクル法に基づいたテレビの正しい処分方法を詳しく解説します。家電量販店での引き取り、指定引取場所への持ち込み、リサイクル料金の仕組みなど、法律に沿った6つの処分方法と具体的な手続きを徹底解説。不法投棄を避け、適切にリサイクルするための完全ガイドです。


\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/
家電リサイクル法とテレビ処分の基本知識
テレビは「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象品目に指定されているため、通常のゴミとして処分することができません。この法律は、限りある資源を有効活用し、廃棄物の適正処理を目的として2001年に施行されました。テレビには鉛やカドミウムなどの有害物質も含まれており、環境への影響を最小限に抑えるために専門的な処理が必要です。
家電リサイクル法の対象となるテレビは、液晶テレビ、プラズマテレビ、ブラウン管テレビの3種類すべてが含まれます。いずれのタイプも一般ゴミや粗大ゴミとして処分することは法律で禁じられているため、必ず指定された方法で処分しなければなりません。違反した場合は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。
テレビを処分するには、主に「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の2種類の費用がかかります。リサイクル料金はメーカーや画面サイズによって異なりますが、一般的に3,000円~5,000円程度が目安です。収集運搬料金は依頼先によって異なり、自分で指定引取場所に持ち込む場合は不要となります。1)2)3)
家電リサイクル法とは何か、テレビが対象となる理由
「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」は、家電製品のリサイクルを促進し、廃棄物の削減と資源の有効活用を図るために制定された法律です。この法律では、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が対象とされています。
テレビが対象品目となった主な理由は、以下の点が挙げられます。まず、テレビには再利用可能な貴重な資源(金、銀、銅、アルミニウムなど)が含まれており、これらを回収することが資源の有効活用につながります。また、特にブラウン管テレビには鉛ガラスなどの有害物質が含まれているため、適切に処理しないと環境汚染を引き起こす可能性があります。
さらに、テレビは比較的大型の家電製品であるため、通常のごみ処理施設では対応が難しく、専用の処理施設が必要となります。こうした背景から、テレビは家電リサイクル法の対象品目として指定され、メーカーに回収・リサイクルの義務が課せられているのです。
家電リサイクル法では、消費者、小売業者、製造業者などの各関係者に役割と責任が明確に定められています。消費者はリサイクル料金を負担し、小売業者は引き取りと製造業者等への引き渡しを担当、製造業者等はリサイクルを実施する義務があります。このシステムにより、テレビを含む対象家電の適正なリサイクルが推進されています。4)5)6)
テレビを処分する際の罰則と不法投棄の問題
テレビを含む家電リサイクル法対象品を不適切に処分した場合、法律に基づいた厳しい罰則が適用されます。一般家庭がテレビを通常のゴミとして出した場合、自治体によっては回収されないだけでなく、悪質なケースでは罰則の対象となる可能性もあります。特に不法投棄は重大な違反であり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)という厳しい罰則が設けられています。
不法投棄の問題は全国的に深刻であり、環境省の調査によれば、毎年数万件の家電リサイクル法対象品の不法投棄が報告されています。不法投棄されたテレビは、風雨にさらされることで内部の有害物質が流出し、土壌や水質の汚染を引き起こす恐れがあります。特にブラウン管テレビに含まれる鉛は環境中に流出すると生態系に深刻な影響を与える可能性があります。
また、不法投棄されたテレビの処理費用は最終的に自治体の負担となり、税金が使われることになります。こうした社会的コストを考慮すると、適切な方法でのリサイクルは単なる法律遵守の問題だけでなく、環境保全と社会的責任の観点からも重要です。
不法投棄を防止するためには、消費者が正しい処分方法を理解し、リサイクル料金の支払いを含めた適切な手続きを行うことが不可欠です。また、無料回収をうたう違法業者に注意することも重要です。こうした業者の中には、回収後に不法投棄を行う悪質なケースも報告されています。7)8)
テレビの正しい処分方法6つの選択肢
テレビを処分する際には、家電リサイクル法に基づいた適切な方法を選ぶ必要があります。大きく分けると、「新しいテレビを購入する際に引き取ってもらう」「以前購入した店舗に依頼する」「自治体指定の回収業者に依頼する」「指定引取場所に自分で持ち込む」「認可を受けた不用品回収業者に依頼する」「リサイクルショップやフリマアプリで売却・譲渡する」の6つの選択肢があります。
それぞれの方法には、費用や手間、手続きの複雑さなどの面で違いがあるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。例えば、新しいテレビを購入予定であれば、購入店での引き取りが最も手間がかからないでしょう。また、車を持っていて時間に余裕がある場合は、指定引取場所への持ち込みが収集運搬料金を節約できる選択肢となります。
いずれの方法を選んでも、最終的にはリサイクル料金が必要になることと、違法な処分は厳しい罰則の対象となることを理解しておきましょう。テレビのリサイクルは、資源の有効活用と環境保全のために欠かせないプロセスであり、社会全体で取り組むべき重要な課題です。9)10)11)
新しいテレビを購入する際の引き取りサービス
新しいテレビを購入する際に、家電量販店や電気店で古いテレビの引き取りサービスを利用することは、最も手間のかからない処分方法の一つです。この方法では、新しいテレビの配達時に同時に古いテレビを回収してもらえるため、別途回収の手配をする必要がなく効率的です。
引き取りサービスを利用する場合は、リサイクル料金と収集運搬料金の両方が必要になります。リサイクル料金は、テレビのメーカーや画面サイズによって異なりますが、一般的に15インチ以下で2,420円、16インチ以上で3,740円程度(税込)が目安です。収集運搬料金は店舗によって設定が異なり、通常1,000円~3,000円程度が相場となっています。
手続きの流れとしては、まず店頭でテレビを購入する際に、古いテレビの引き取りを希望する旨を伝えます。その場でテレビのメーカー、サイズ、製造年などの情報を元にリサイクル料金と収集運搬料金の見積もりが出され、料金を支払います。支払い時に家電リサイクル券が発行され、配達日に回収が行われる流れです。
このサービスを利用する際のポイントとして、配達と回収を同日に行うのが一般的ですが、事前に店舗に確認しておくとよいでしょう。また、一部の家電量販店では独自のポイントサービスを利用して割引が受けられる場合もあります。新しいテレビと古いテレビが同一メーカーの場合、一部のメーカーでは引き取り料金の割引を行っている場合もあるため、事前に問い合わせることをおすすめします。12)13)14)
以前テレビを購入した店舗での回収依頼
以前にテレビを購入した店舗に回収を依頼する方法は、新品購入を伴わない場合でも利用できる便利な選択肢です。家電リサイクル法では、過去に販売した特定家庭用機器(テレビを含む)の引き取りは、小売業者の義務として定められています。そのため、購入した店舗であれば基本的に回収を拒否することはできません。
この方法を利用する場合、まず購入した店舗に電話やウェブサイトで問い合わせを行い、回収の申し込みをします。申し込み時には、テレビのメーカー、画面サイズ、型番などの情報を伝える必要があります。その後、店舗側から回収日時の提案があり、当日スタッフが自宅まで訪問して回収を行います。
費用としては、リサイクル料金に加えて収集運搬料金が必要になります。リサイクル料金は製造メーカーや画面サイズによって異なりますが、収集運搬料金は店舗ごとに独自に設定されており、地域や回収の難易度(階段の有無、エレベーターの有無など)によって変動する場合もあります。一般的には1,000円~3,000円程度が相場です。
注意点として、購入時のレシートや保証書がなくても基本的には回収を依頼できますが、一部の店舗では購入証明を求められる場合もあります。また、テレビを購入した店舗が閉店している場合は、同一チェーンの別店舗で対応してもらえることが多いです。店舗の統合や業態変更があった場合も、継承した企業に引き取り義務が移行するため、事前に確認すると良いでしょう。15)16)
自治体指定の回収業者を利用する方法
一部の自治体では、家電リサイクル法対象品目であるテレビの回収サービスを独自に提供している場合があります。このサービスは、自治体が指定した回収業者が家庭を訪問し、テレビを回収するというものです。自治体主導のサービスであるため、信頼性が高く、適正な処理が期待できる点が大きなメリットです。
自治体の回収サービスを利用するには、まず居住している自治体のウェブサイトや窓口で、サービスの有無と申し込み方法を確認します。サービスを提供している場合は、電話やインターネット、窓口での申し込みが可能です。申し込み時には、テレビのメーカー、サイズ、製造年などの情報を伝える必要があります。
費用面では、リサイクル料金に加えて自治体が定めた収集運搬料金がかかります。この収集運搬料金は自治体によって異なりますが、一般的には民間の回収業者よりも安価に設定されていることが多いです。支払い方法も自治体によって異なり、事前に振込を求められる場合や、回収時に現金で支払う場合などがあります。
ただし、自治体のサービスには制約もあります。例えば、回収日時が限定されていたり、申し込みから回収までに時間がかかる場合があります。また、自治体によってはサービス対象地域が限られていたり、年に数回の特定期間のみの実施である場合もあります。さらに、すべての自治体がこのサービスを提供しているわけではないため、事前に確認が必要です。17)18)
自治体がテレビの回収を行っているかどうかはどこで確認できる
自治体がテレビの回収サービスを行っているかどうかを確認する方法はいくつかあります。最も確実な方法は、お住まいの自治体の公式ウェブサイトを確認するか、直接自治体の廃棄物担当課(清掃課、環境課、資源循環課など)に問い合わせることです。
自治体の公式ウェブサイトでは、通常「ごみ・リサイクル」「廃棄物」「家電リサイクル」などのカテゴリで関連情報を掲載しています。サイト内検索で「テレビ 処分」「家電リサイクル」などのキーワードを入力すると、該当ページが表示されることが多いです。ここでは、自治体独自の回収サービスの有無、申し込み方法、料金体系などが確認できます。
電話での問い合わせは、市役所・区役所・町村役場の代表番号に連絡し、家電リサイクルについての問い合わせだと伝えれば、担当部署に繋いでもらえます。また、自治体が発行する「ごみ分別カレンダー」や「ごみ分別ガイドブック」にも関連情報が記載されていることがあります。
自治体によっては、一般的な家電リサイクル法に基づく処分方法の案内だけでなく、独自の支援制度を設けている場合もあります。例えば、収集運搬料金の補助制度や、指定した日時に特定の場所でテレビを含む家電製品を回収する「拠点回収」を実施している自治体もあります。
回収サービスの内容や料金は自治体によって大きく異なるため、複数の処分方法の中から最適なものを選ぶためにも、まずは自治体の情報を正確に把握することが重要です。19)20)21)
指定引取場所に自分で持ち込む方法
指定引取場所(RKC:リサイクルプラント)に自分でテレビを持ち込む方法は、収集運搬料金を節約できる経済的な選択肢です。この方法では、事前に家電リサイクル券を購入し、自分でテレビを運搬して指定引取場所に持ち込みます。
手続きの流れとしては、まず郵便局で家電リサイクル券を購入する必要があります。購入時には、テレビのメーカー、画面サイズ、シリアル番号などの情報が必要で、これらの情報と共にリサイクル料金を支払います。この時点で受け取る家電リサイクル券の控えは、後日テレビをきちんと処理したことを証明する重要な書類となるので、大切に保管しておきましょう。
次に、購入した家電リサイクル券をテレビに貼り付け、指定引取場所に運搬します。指定引取場所は全国各地に設置されており、一般財団法人家電製品協会のウェブサイトで検索することができます。持ち込み前に、営業時間や持ち込み可能日、必要書類などを事前に確認しておくと安心です。
この方法の最大のメリットは、収集運搬料金が不要となる点です。一般的に収集運搬料金は1,000円~3,000円程度かかるため、かなりの節約になります。ただし、デメリットとしては自分で運搬する必要があるため、車両の手配や重いテレビの運搬に伴う労力、時間の確保などが必要になります。特に大型テレビの場合は、一人での作業が困難なこともあるため、手伝いを頼めるかどうかも考慮する必要があります。22)23)24)
リサイクル券を購入した後、テレビを回収業者に引き渡す手順は
リサイクル券を購入した後、テレビを回収業者に引き渡す具体的な手順について解説します。この流れは主に「指定引取場所に自分で持ち込む」または「自治体指定の回収業者」を利用する場合に該当します。
まず、購入した家電リサイクル券はテレビ本体に確実に貼り付けます。具体的には、券面に記載されている「家電メーカー等保管用」「お客様控」以外の部分を本体に貼り付けます。券が汚れたり破れたりしないよう、しっかりと貼ることが重要です。貼り付け位置は特に指定されていませんが、回収時に確認しやすい場所(背面など)が望ましいでしょう。
指定引取場所に自分で持ち込む場合は、営業時間内に指定引取場所に到着し、受付で必要事項を記入します。この際、家電リサイクル券のお客様控えが必要となるので必ず持参してください。受付後、スタッフの指示に従ってテレビを指定された場所に置き、引き渡し完了となります。受領書やスタンプを押した控えをもらうことで、正式に引き渡し手続きは完了します。
自治体指定の回収業者や許可を受けた廃棄物収集運搬業者に依頼する場合は、事前に予約した日時に業者が自宅に訪問します。その際、リサイクル券を貼り付けたテレビを業者に引き渡します。この時、業者から受領書や引取証明書などが発行されるのが一般的です。この書類は、適正に処理されたことの証明となるため、一定期間保管しておくことをおすすめします。
なお、引き渡し時には特に大型テレビの場合、搬出を手伝う必要があるかどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。また、テレビ本体以外の付属品(リモコン、取扱説明書など)については、基本的には一緒に引き取ってもらえますが、細かい規定は業者によって異なる場合があるため、事前確認が推奨されます。25)26)
適正な不用品回収業者への依頼方法
不用品回収業者に依頼してテレビを処分する方法は、手間をかけずに自宅から回収してもらえる便利な選択肢です。しかし、この方法を選ぶ際には、業者の適正さを確認することが非常に重要です。無許可業者による不適切な処理や高額請求などのトラブルを避けるためにも、以下のポイントを押さえて業者を選びましょう。
まず、業者選びで最も重要なのは「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っているかどうかです。この許可は各自治体が発行するもので、許可を持つ業者は法律に基づいた適正な処理を行う義務があります。許可証の確認は、業者のウェブサイトで許可番号が公開されているか、または直接問い合わせて確認するとよいでしょう。
料金体系も重要なチェックポイントです。適正な業者は、リサイクル料金と収集運搬料金を明確に区分して提示します。リサイクル料金は法律で定められた金額であり、これを不当に安く提示する業者は違法な処理を行っている可能性があります。特に「無料回収」をうたう業者には注意が必要です。
業者への依頼手順としては、まず電話やウェブサイトで見積もりを依頼します。その際、テレビのメーカー、サイズ、設置場所(階数や搬出経路など)を伝え、詳細な料金を確認します。料金に納得できれば回収日時を予約し、当日は業者がテレビを回収していきます。この時、家電リサイクル券の控えや受領証を必ず受け取り、保管しておきましょう。
適正な業者を選ぶことで、法律に準拠した処理が行われ、環境保全に貢献できるだけでなく、個人情報の漏洩リスクも軽減できます。特にテレビにはチャンネル履歴など、意外な個人情報が残っている可能性もあるため、信頼できる業者に依頼することは重要です。27)28)
リサイクルショップやフリマアプリでの売却・譲渡
まだ使用可能な状態のテレビであれば、リサイクルショップへの売却やフリマアプリ、オークションサイトでの取引も選択肢として考えられます。この方法では、リサイクル料金が不要になるだけでなく、状態が良ければ収入を得ることも可能です。
リサイクルショップに売却する場合は、まず店舗に電話やウェブサイトで問い合わせ、買取可能かどうかを確認します。多くのショップでは、製造から数年以内のモデルで、傷や汚れが少なく正常に動作するテレビを買取対象としています。特に人気メーカーや高機能モデル、大画面テレビは買取価格が高くなる傾向があります。買取の際は、リモコンや取扱説明書、付属品がそろっていると価格アップにつながることが多いです。
フリマアプリやオークションサイトでの売却は、仲介手数料はかかるものの、店舗買取よりも高額で売れる可能性があります。出品する際は、明確な製品情報(メーカー、型番、画面サイズ、購入年など)と共に、実際の動作状況や傷・汚れの有無などを正直に記載することが重要です。また、複数の角度からの写真や、実際に映像を映した状態の写真があると購入検討者の安心感につながります。
譲渡の選択肢としては、地域の掲示板やSNSグループ、フリマアプリの「譲ります」カテゴリなどを利用する方法があります。特に学生や単身世帯など、中古品でも問題ない層へのニーズがあります。譲渡の場合も、テレビの状態や受け渡し方法を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
いずれの方法でも、個人情報保護のため、売却・譲渡前にテレビの設定をリセットしておくことをおすすめします。特に、インターネット接続機能を持つ機種では、アカウント情報や履歴を削除しておくことが重要です。29)30)


\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/
テレビ処分時の費用と家電リサイクル券
テレビを適切に処分するためには、主に「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の2種類の費用がかかります。リサイクル料金は、テレビを再資源化するための処理費用であり、家電リサイクル法に基づいて製造メーカーごとに設定されています。収集運搬料金は、テレビを消費者から指定引取場所まで運搬するためのコストで、回収業者や小売店が独自に設定しています。
家電リサイクル券は、これらの費用の支払いを証明し、適正な処理を確保するための重要な書類です。この券は、消費者がリサイクル料金を支払った証明となるだけでなく、テレビの処理過程を追跡するためのツールとしても機能しています。
家電リサイクル券の入手方法には、主に「料金販売店回収方式」と「料金郵便局振込方式」の2つがあります。前者は家電小売店で料金を支払い、その場で券を発行してもらう方法で、後者は郵便局で料金を支払い、その場で券を受け取る方法です。どちらの方式を選ぶかは、テレビの処分方法によって異なります。
これらの費用や手続きは一見煩雑に感じるかもしれませんが、環境保全と資源の有効活用のために必要なシステムです。適切な処理により、テレビに含まれる貴重な資源が回収され、有害物質による環境汚染を防ぐことができます。31)32)
テレビを処分する際のリサイクル料金はどれくらい
テレビを処分する際のリサイクル料金は、メーカーや画面サイズ、テレビの種類(ブラウン管、液晶・プラズマ)によって異なります。ここでは、一般的なリサイクル料金の相場と、その料金体系について詳しく解説します。
リサイクル料金の基本的な枠組みは以下の通りです:
【ブラウン管テレビ】
- 15型以下:1,870円(税込2,057円)
- 16型以上:2,970円(税込3,267円)
【液晶・プラズマテレビ】
- 15型以下:1,870円(税込2,057円)
- 16型以上:3,400円(税込3,740円)
これらの料金は、メーカーによって若干の違いがあります。例えば、ソニーやパナソニック、シャープ、東芝などの大手メーカーは同程度の料金設定ですが、一部の海外メーカーや小規模メーカーでは料金が異なる場合があります。
また、上記の料金はいわゆる「Aグループ」(国内主要メーカー)の料金で、メーカー不明や倒産メーカーのテレビは「Bグループ」として異なる料金体系が適用されることもあります。この場合、家電リサイクル券センターが料金を設定しており、基本的にはAグループと同等かやや高めの料金となっています。
リサイクル料金は、テレビに含まれる資源を再利用するための分解・選別作業の費用や、有害物質の適正処理費用などに充てられています。特にブラウン管テレビには鉛を含むガラスが使用されており、その処理には特別な技術と設備が必要となるため、処理コストが発生します。
なお、リサイクル料金は定期的に見直されることがあるため、最新の料金については一般財団法人家電製品協会のウェブサイトや、処分を依頼する小売店で確認するとよいでしょう。33)34)35)
家電リサイクル券の種類と取得方法
家電リサイクル券は、テレビなどの対象家電をリサイクルするために必要な証明書であり、主に2種類の取得方法があります。それぞれの特徴と手続きの流れを詳しく解説します。
【料金販売店回収方式】 この方式は、家電量販店や電気店など小売業者を通じてテレビを引き取ってもらう場合に利用する方法です。店舗でテレビの引き取りを依頼する際に、リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、その場で家電リサイクル券が発行されます。この券の一部は控えとして消費者に渡され、残りは回収されるテレビに貼付されます。
この方式のメリットは、手続きが一度で完結する点と、テレビの搬出から処分までの全工程を小売業者に任せられる点です。ただし、収集運搬料金が別途必要となるため、総費用は高くなりがちです。
【料金郵便局振込方式】 この方式は、自分で指定引取場所にテレビを持ち込む場合や、自治体指定の回収業者を利用する場合に選択する方法です。まず、郵便局に備え付けの「家電リサイクル券」に必要事項(氏名、住所、電話番号、テレビのメーカー名、型番、製造番号など)を記入し、リサイクル料金を支払います。支払い後、家電リサイクル券が発行され、その一部を控えとして保管し、残りをテレビに貼付します。
この方式のメリットは、収集運搬料金を節約できる点です。特に自分で指定引取場所にテレビを持ち込む場合は、収集運搬料金が不要となるため、費用を最小限に抑えることができます。ただし、郵便局での手続きと、テレビの運搬を自分で行う手間がかかります。
どちらの方式でも、家電リサイクル券の控えは適切に処理されたことを証明する重要な書類となるため、一定期間保管しておくことが推奨されます。また、インターネットでリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券を発行する「インターネット家電リサイクル申込」というサービスも一部地域で提供されています。36)37)
リサイクル券を購入する際の注意点は
家電リサイクル券を購入する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを事前に把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
【必要情報の事前確認】 リサイクル券の購入には、テレビに関する詳細情報が必要です。具体的には、メーカー名、画面サイズ(型数)、製造番号などが求められます。特に製造番号は、テレビの背面や底面に記載されていることが多いため、事前に確認しておくと良いでしょう。製造番号が不明な場合でも手続きは可能ですが、その旨を伝える必要があります。
【料金の正確な把握】 リサイクル料金はメーカーや型式によって異なります。事前に一般財団法人家電製品協会のウェブサイトで料金を確認しておくと、余分な費用の準備や不足による再訪問の手間を省けます。郵便局での支払いは現金のみとなるため、必要な金額を用意しておきましょう。
【記入ミスの防止】 家電リサイクル券の記入欄は複数あり、間違いが許されません。特に、氏名、住所、電話番号などの個人情報や、テレビの情報は正確に記入する必要があります。氏名や住所は、収集運搬業者がテレビを回収する際の確認に使用されるため、誤りがあると引き取りを拒否される可能性もあります。
【控えの保管】 家電リサイクル券には「お客様控え」部分があり、これは処理が完了したことを証明する重要な書類です。紛失しないよう、安全な場所に一定期間(少なくとも数ヶ月間)保管することが推奨されます。この控えは、後日自治体から不法投棄の疑いで問い合わせがあった場合など、適正に処理したことを証明する証拠となります。
【インターネット申し込みの活用】 近年は、インターネットを通じて家電リサイクル券を申し込めるサービス「インターネット家電リサイクル申込」も提供されています。このサービスでは、自宅のパソコンやスマートフォンから24時間申し込みが可能で、クレジットカードでの支払いにも対応しています。ただし、利用可能地域が限られている場合があるため、事前確認が必要です。38)39)40)
テレビのメーカーが不明の場合、どのように処分すればいい
テレビのメーカーが不明の場合や、製造メーカーが倒産・撤退した場合でも、家電リサイクル法に基づいた適切な処分が必要です。このような「メーカー不明・不存在」のテレビは、一般的に「Bグループ」と呼ばれる区分で処理されます。
「Bグループ」のテレビを処分する基本的な手続きは、メーカーが明確な場合(Aグループ)と同じです。具体的な手順は以下の通りです:
- テレビのメーカー名が本体に表示されているか確認します。古いテレビや海外製品では、メーカー名が不明瞭な場合があります。
- メーカー名が確認できない場合は、「製造者等不存在製品」または「メーカー不明」としてリサイクル手続きを行います。
- 家電量販店での引き取り、自治体指定の回収業者への依頼、指定引取場所への持ち込みなど、通常のテレビと同じ処分方法を選択できます。
- リサイクル料金は、一般財団法人家電製品協会が設定した料金(Bグループ料金)が適用されます。
Bグループのリサイクル料金は、Aグループ(主要メーカー)とほぼ同等か、若干高めに設定されていることが一般的です。例えば、2024年現在の料金体系では、以下のような設定となっています:
- ブラウン管テレビ(15型以下):1,870円(税込2,057円)
- ブラウン管テレビ(16型以上):2,970円(税込3,267円)
- 液晶・プラズマテレビ(15型以下):1,870円(税込2,057円)
- 液晶・プラズマテレビ(16型以上):3,400円(税込3,740円)
郵便局で家電リサイクル券を購入する場合は、メーカー欄に「製造者等不存在製品」または「メーカー不明」と記入します。家電量販店や小売店に依頼する場合は、スタッフに「メーカーが不明である」旨を伝えれば、適切な手続きを行ってくれます。
なお、海外製のテレビでも日本国内で正規に販売されていれば、輸入業者がリサイクルの責任を負います。このような場合は、購入時の書類(保証書、取扱説明書など)で輸入業者を確認できることがあります。これが確認できれば、その輸入業者名でリサイクル手続きを行うことも可能です。41)42)43)
テレビ処分のよくある質問と注意点
テレビの処分には様々な疑問や注意点がつきものです。ここでは、多くの方が抱きがちな疑問について答えるとともに、スムーズな処分のための重要なポイントをまとめます。
まず、よくある質問として「テレビに付属するリモコンや取扱説明書、アンテナケーブルなどはどうすればよいか」という点があります。基本的には、これらの付属品はテレビと一緒に引き取ってもらえることが多いですが、一部の回収業者では別途料金が発生する場合もあります。事前に確認しておくと安心です。
また、「処分するテレビの中にある個人情報は大丈夫か」という懸念を持つ方も多いでしょう。近年のスマートテレビには、インターネット接続履歴やログイン情報など、様々な個人情報が保存されている可能性があります。処分前に、必ず設定の初期化(ファクトリーリセット)を行いましょう。詳しい方法は、各メーカーの取扱説明書やウェブサイトで確認できます。
さらに重要な注意点として、「無料回収」をうたう業者には十分注意が必要です。家電リサイクル法では、テレビの適正処理にはコストがかかるため、正規の方法では必ずリサイクル料金が発生します。無料や著しく安い料金で回収を行う業者の中には、不法投棄や不適正処理を行う違法業者も存在します。こうした業者に依頼した場合、環境汚染の一因となるだけでなく、依頼者も罰則の対象となる可能性があります。44)45)
不法投棄を避けるための対策
テレビの不法投棄は深刻な環境問題を引き起こすだけでなく、法律違反として厳しい罰則の対象となります。ここでは、不法投棄を防ぐための対策と、適正処理の重要性について解説します。
不法投棄の最大の原因の一つは、リサイクル料金や収集運搬料金の負担を避けたいという心理です。しかし、テレビには有害物質が含まれており、適切に処理されなければ環境汚染や健康被害のリスクがあります。また、不法投棄された廃棄物の処理費用は最終的に税金で賄われることになり、社会全体の負担となります。
不法投棄を防ぐための具体的な対策としては、まず正規の処分方法についての正確な知識を持つことが重要です。本記事で紹介した6つの処分方法はいずれも法律に則ったものであり、これらを利用することで環境保全に貢献できます。特に費用面で悩む場合は、指定引取場所への直接持ち込みや、新品購入時の引き取りサービスの活用など、比較的経済的な選択肢を検討してみましょう。
また、無料回収をうたう業者への安易な依頼は避けるべきです。家電リサイクル法では、テレビの適正処理には必ずコストがかかるため、正規の方法では必ずリサイクル料金が発生します。無料や著しく安い料金で回収を行う業者の中には、回収後に不法投棄を行う悪質な業者も存在します。認可を受けた業者かどうか、リサイクル料金と収集運搬料金が明確に区分されているかなどを確認することが重要です。
不法投棄を発見した場合は、地域の環境課や清掃課など、廃棄物担当部署に通報することも社会的な責任です。不法投棄された廃棄物の早期発見と対応は、環境被害の拡大を防ぐ上で重要な役割を果たします。
最後に、家電リサイクル券の控えはしっかりと保管しておきましょう。これは適正に処理したことの証明となり、万が一不法投棄の疑いをかけられた場合の証拠となります。46)47)48)
リサイクルによるテレビの資源有効活用
テレビを適切にリサイクルすることは、資源の有効活用と環境保全の両面で大きな意義があります。ここでは、テレビのリサイクルによってどのような資源が回収され、どのように再利用されているのかを解説します。
テレビ、特にブラウン管テレビには、ガラス、プラスチック、銅、アルミニウム、鉄、金、銀など様々な素材が使用されています。例えば、ブラウン管には大量のガラスが使用されており、適切に処理することで新たなガラス製品の原料として再利用できます。また、液晶テレビのバックライトには水銀が使用されているケースがあり、これを適切に回収することで環境汚染を防止します。
特に注目すべきは、テレビに含まれる「レアメタル(希少金属)」です。基板などの電子部品には、金、銀、白金、パラジウムなどの貴金属やレアメタルが含まれています。これらの金属は地球上での埋蔵量が限られており、採掘には大きな環境負荷がかかるため、リサイクルによる回収が極めて重要です。
家電リサイクル法に基づくリサイクルプロセスでは、まずテレビを手作業と機械を組み合わせて解体し、素材ごとに分別します。その後、それぞれの素材に適した処理方法で再資源化が行われます。金属類は溶解して新たな金属製品の原料となり、プラスチックは燃料や新たなプラスチック製品の原料として活用されます。
2001年の家電リサイクル法施行以降、リサイクル率(再資源化率)は年々向上しており、現在では対象品目全体で70%を超えるリサイクル率を達成しています。特にテレビに関しては、ブラウン管テレビで約55%、液晶・プラズマテレビで約74%のリサイクル率となっています。
このように、テレビを適切にリサイクルすることは、限りある資源の有効活用につながるだけでなく、新たな資源の採掘に伴う環境負荷を低減し、廃棄物の最終処分量を削減する効果があります。一人ひとりが正しい処分方法を選ぶことが、持続可能な社会の実現に貢献します。49)50)
まとめ:テレビの処分方法選びのポイント
テレビの処分は、法律に基づいた適切な方法で行うことが重要です。本記事で紹介した6つの処分方法(新品購入時の引き取り、購入店での回収、自治体指定の回収業者、指定引取場所への持ち込み、適正な不用品回収業者、リサイクルショップなどでの売却・譲渡)は、いずれも家電リサイクル法に準拠した正しい選択肢です。
処分方法を選ぶ際のポイントとしては、まず「費用」と「手間」のバランスを考慮することが大切です。例えば、自分で指定引取場所に持ち込む方法は収集運搬料金が不要となり経済的ですが、車両の手配や運搬の労力が必要です。一方、小売店や回収業者に依頼する方法は収集運搬料金がかかるものの、手間が少なく済みます。
また、「処分の緊急性」も重要な判断基準です。自治体指定の回収や小売店での引き取りは予約から回収までに時間がかかることがあります。急いで処分したい場合は、指定引取場所への持ち込みや不用品回収業者への依頼が適しています。
テレビの状態や価値によっても最適な方法は異なります。まだ使える状態の比較的新しいテレビであれば、リサイクルショップでの買取やフリマアプリでの売却を検討する価値があります。これにより、リサイクル料金の負担を避けつつ、場合によっては収入を得ることも可能です。
どの方法を選ぶ場合でも、必ず事前に料金や手続き、必要書類などを確認しておくことが重要です。また、家電リサイクル券の控えは、適正に処理したことの証明となるため、一定期間保管しておきましょう。
テレビの適切な処分は、資源の有効活用と環境保全につながる重要な取り組みです。一人ひとりが責任を持って行動することで、持続可能な循環型社会の実現に貢献できるのです。51)52)53)
テレビ処分方法選びのための判断フローチャート
テレビの処分方法を選ぶ際の判断基準を、フローチャート形式でまとめてみました。自分の状況に最適な処分方法を見つける参考にしてください。
- 新しいテレビを購入予定がありますか?
- はい → 購入店での引き取りサービスを利用(最も手間がかからない)
- いいえ → 2へ進む
- 処分するテレビは正常に動作しますか?
- はい → リサイクルショップでの買取やフリマアプリでの売却を検討(リサイクル料金が不要で、収入を得られる可能性あり)
- いいえ → 3へ進む
- 以前テレビを購入した店舗を覚えていますか?
- はい → 購入店に回収を依頼(法律で引き取り義務があるため確実)
- いいえ → 4へ進む
- 自分でテレビを運搬できますか?(車両の確保や人手など)
- はい → 指定引取場所に持ち込む(収集運搬料金が不要で経済的)
- いいえ → 5へ進む
- お住まいの自治体に家電リサイクル品の回収サービスはありますか?
- はい → 自治体指定の回収業者に依頼(信頼性が高く、比較的安価)
- いいえ → 6へ進む
- 処分の緊急性はありますか?
- はい → 認可を受けた不用品回収業者に依頼(即日対応可能な場合が多い)
- いいえ → お住まいの地域の指定引取場所や料金を確認し、コストと手間のバランスを考慮して最適な方法を選択
このフローチャートはあくまで目安です。実際の選択にあたっては、料金、手間、信頼性、緊急性などを総合的に判断することが重要です。また、どの方法を選ぶ場合でも、家電リサイクル法に基づいた適正な処理を行うことで、環境保全と資源の有効活用に貢献できます。
特に注意すべき点として、「無料回収」をうたう未認可業者には依頼しないようにしましょう。これらは不法投棄や不適正処理につながる可能性があり、依頼者も罰則の対象となるケースがあります。必ず公的機関や認可を受けた業者を通じて、適正な処理を行いましょう。54)55)56)


\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/
参考文献
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」
- Curama「テレビの処分方法」
- トラッシュアップ「液晶テレビの処分方法」
- 経済産業省「家電リサイクル法の概要」
- 一般財団法人家電製品協会「家電リサイクル法について」
- 環境省「家電リサイクル法の解説」
- 環境省「不法投棄防止について」
- 一般財団法人家電製品協会「不法投棄防止への取り組み」
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「テレビの処分方法」
- Kado-de「テレビの処分方法」
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「テレビの処分方法」
- 経済産業省「家電リサイクル法の解説」
- 一般財団法人家電製品協会「テレビの処分方法」
- Kado-de「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「テレビの処分方法」
- Kado-de「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「自治体の取り組み」
- 経済産業省「家電リサイクル法の解説」
- 環境省「家電リサイクル法の解説」
- 一般財団法人家電製品協会「指定引取場所について」
- 家電リサイクル券センター「郵便局での振込方法」
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「リサイクル券の使い方」
- 家電リサイクル券センター「郵便局での振込方法」
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」
- 環境省「適正な廃棄物処理業者の選び方」
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」
- Kado-de「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「リサイクル料金について」
- 家電リサイクル券センター「家電リサイクル券について」
- 一般財団法人家電製品協会「リサイクル料金一覧」
- 家電リサイクル券センター「リサイクル料金について」
- ヤマダ電機「家電リサイクルについて」
- 家電リサイクル券センター「郵便局での振込方法」
- 一般財団法人家電製品協会「家電リサイクル券の取得方法」
- 家電リサイクル券センター「リサイクル券購入時の注意点」
- 一般財団法人家電製品協会「家電リサイクル券の取り扱い」
- ヤマダ電機「家電リサイクルについて」
- 一般財団法人家電製品協会「メーカー不明の場合の処分方法」
- 家電リサイクル券センター「製造者等不存在製品について」
- 経済産業省「家電リサイクル法Q&A」
- 一般財団法人家電製品協会「よくある質問」
- 環境省「家電リサイクル法に関するQ&A」
- 環境省「不法投棄防止への取り組み」
- 一般財団法人家電製品協会「不法投棄対策」
- 経済産業省「不法投棄の防止について」
- 一般財団法人家電製品協会「リサイクルの流れ」
- 環境省「家電リサイクル制度の成果」
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「テレビの処分方法」
- Kado-de「テレビの処分方法」
- 一般財団法人家電製品協会「家電リサイクル法の対象品目」
- 経済産業省「家電リサイクル法の概要」
- ジャパネットたかた「テレビの処分方法」








