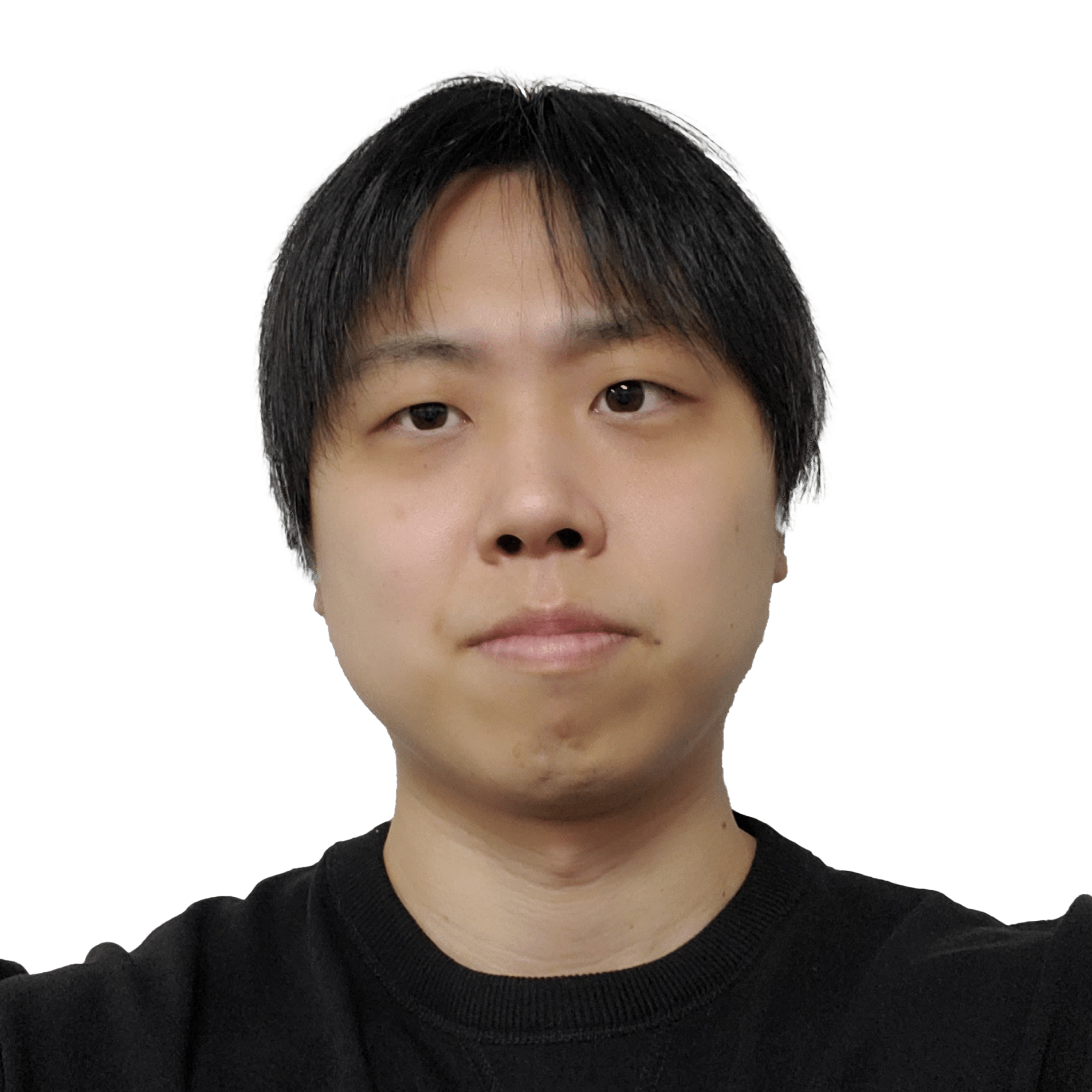住宅ローンの金利とは?仕組みや返済額をシミュレーションで解説

「住宅ローンの金利ってなに?」「住宅ローンの仕組みを教えて!」住宅の購入や、すでに住宅ローンを利用している方で疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、住宅ローンの金利の意味や仕組み、金利タイプや返済シミュレーションを解説します。住宅ローンについて疑問や不安を抱いている方は、ぜひ最後までご覧ください。
住宅ローンの金利とは?初心者向けにわかりやすく解説
まずは、住宅ローン金利の意味を解説します。そもそもの「金利」の意味や、金利の違いによる返済額の差も確認しておきましょう。
- 金利はお金を借りる際の「借り賃」
- 月々の返済額や総支払額に大きく関わる
- わずか0.1%の差でも、数十万円の違いになることも
金利はお金を借りる際の「借り賃」
金利は、お金を借りるときにかかる「借り賃」のようなものです。住宅ローンでは、借りた額に応じて利息を上乗せして返済します。例えば、1,000万円を年利1%で借りた場合、初年度の利息は約10万円です。
金利は毎月の返済額や総支払額に大きく影響するため、少しの違いでも負担に差が出ます。借りる時期や金融機関によって金利は変わるので、家を買う前に基本を知っておくと安心です。
月々の返済額や総支払額に大きく関わる
金利は住宅ローンの返済額に大きく影響します。例えば、金利が1%か2%かによって、同じ借入額でも総支払額が数十万〜数百万円変わることがあります。毎月の返済も増えるため、家計への負担にも直結します。
見た目は低く感じる金利でも、優遇条件の終了後に上がる場合もあるため注意が必要です。借入前に返済シミュレーションを行い、月々の負担や最終的な支払額を確認しておくことが大切です。
わずか0.1%の差でも数十万円の違いになることも
わずか0.1%の金利差でも返済額は大きく変わります。例えば、3,000万円を35年返済で借りた場合、金利1.0%なら月々約84,685円。1.1%だと約87,207円になり、月々は約2,500円の差となります。総額では約106万円も違ってきます。
金利は小さな数字でも家計への影響が大きいため、住宅ローンを選ぶときは返済総額までしっかり比較しましょう。
住宅ローン金利の仕組み|よく出る5つの用語
住宅ローン金利には以下5つの種類があります。
- 基準金利
- 優遇金利
- 適用金利
- 当初金利
- 通期金利
それぞれで意味が異なるため、詳しく解説します。金利の仕組みを理解して、金利への不安を払拭しましょう。
「基準金利」は銀行が設定する基礎となる金利
住宅ローン金利の基準になるのが「基準金利」です。これは銀行が独自に定めた金利で、そこからどれだけ引き下げられるかで、実際に借りられる金利が決まります。
例えば、店頭金利が高く見えても、優遇によって低い金利が適用される場合もあります。ただし、優遇幅は人や借入条件で異なるため、事前に確認が必要です。銀行ごとに基準金利の水準は異なり、時期によって見直されることもあります。金利の仕組みを理解して比較しましょう。
「優遇金利」は条件に応じて引き下げられる割引金利
優遇金利とは、実際に適用される割引後の金利のことです。住宅ローンの金利は、まず「基準金利」があり、そこから銀行が設定する「優遇幅」に応じて割引されます。この割引後の金利が「優遇金利」です。
ただし、優遇金利を受けるには条件が必要です。例えば、給与振込を同じ銀行に設定したりクレジットカードを作成したりすると、金利が基本より低くなる場合があります。
優遇幅は人や銀行によって異なるため、事前に複数の銀行で比較し、自分に合ったローンを選ぶことが大切です。金利が低くなるからといって安心せず、総返済額や将来の変動リスクも踏まえて判断しましょう。
「適用金利」は実際に支払う金利
適用金利とは、実際にローン契約で適用される最終的な金利のことです。
広告で目にする金利は、もともとの「基準金利」から優遇が適用された後の数字である場合が多く、誰でも同じ金利になるわけではありません。適用金利は、年収や信用情報、借入額などによって個別に決まります。少しの差でも総返済額に大きく影響するため、自分の適用金利を事前に確認し、金利の仕組みを理解したうえで選ぶことが大切です。
「当初金利」と「通期金利」の違いを比較
当初金利は借り始めてから一定期間だけ低く、その後に引き上げられる仕組みです。一方、通期金利は、借入中ずっと同じ優遇幅が続きます。例えば、当初5年だけ低金利の場合、最初は返済が楽でも、その後に急に負担が増えることがあります。
その点、通期型は金利の優遇がずっと続くため、将来の見通しを立てやすいのが特長です。ただし、最初の金利は当初型より高く感じる場合もあります。収入や生活設計に合わせて選ぶのが重要です。
低金利の見せ方に惑わされないために知っておきたいこと
住宅ローンの広告において、「金利0.3%!」などの目を引く広告を目にすることがありますが、低金利の見せ方惑わされないように注意しましょう。それが一部の期間だけの「当初金利」である可能性があります。このケースの場合、期間終了後に金利が大きく上がることもあるため、見た目の数字だけで判断すると、将来的に返済額が増えてしまうリスクがあります。
また、「最大優遇」などの条件も要注意です。実際には、給与振込やクレジットカード利用、一定額以上の借入などの条件を満たさなければ、その金利にならないこともあります。
大切なのは、「自分に適用される金利はいくらか」「優遇はどれくらい続くか」「変動時のリスクがどれくらいあるか」を具体的に把握することです。気になる点は必ず事前に金融機関に確認しましょう。
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

安心できる住宅予算の出し方とは?
住宅購入で何より大切なのは、住宅ローンの重圧から自由になる「資金計画」です。オンラインセミナー「小さいリスクで家を買う方法」では、お金の専門家による「安心予算」の算出方法を公開。
家を買うことは豊かな人生のための手段です。無理なく家を購入し、その後の暮らしも楽しみませんか?
金利タイプは3種類|それぞれの特徴と違い
金利には以下3つのタイプがあります。
- 固定金利
- 変動金利
- 固定期間選択型
それぞれでメリットやデメリットが異なるので詳しく解説します。
固定金利:完済までずっと変わらず安心
固定金利とは、借入時に決まった金利が最後まで変わらないタイプです。将来の返済額が早くから分かるため、計画を立てやすく、家計管理にも向いています。金利が上がっても影響を受けにくく、返済が安定する点が大きなメリットです。
ただし、変動金利より初めの金利が高めになりやすく、市場金利が下がっても返済額は減りません。毎月の支払いに波がないため、安定を重視する人に選ばれています。
変動金利:金利は低めだが途中で変わる可能性あり
変動金利とは、借り始めの金利が低めに設定されており、返済の初期負担を抑えやすいのが特徴です。ただし、金利は半年ごとに見直され、将来の支払額が上がるリスクがあります。
多くの住宅ローンでは5年ごとに返済額を見直し、増加額に上限を設けて急な負担増を防ぐ仕組みもあります。それでも長期的な支払額は読みにくいため、金利変動に強く、余裕を持って返済できる人に向いています。
固定期間選択型:一定期間は固定、その後は変動になる
固定期間選択型とは、最初に決めた年数だけ金利が固定され、その後は変動金利に切り替わる仕組みです。例えば、10年間は返済額が変わらなくても、その後は市場の金利動向によって増減します。
家計に余裕があるうちは、繰り上げ返済を進めると後の負担を軽くしやすくなります。なお、固定期間終了後の金利は自動で決まるのではなく、金融機関との再契約が必要な場合もあるため、契約前に内容をよく確認しておくことが大切です。
金利タイプ選びで後悔しないための3つのポイント
3つの金利タイプを解説しましたが、実際に選ぶ際は以下3つのポイントを押さえましょう。
- 家計に余裕はあるか?金利変動の影響に備えられるか
- 将来の金利上昇リスクへの備えはあるか
- 「安心重視」・「低コスト重視」のどちらを重視するか
それぞれを詳しく解説します。
家計に余裕はあるか?金利変動の影響に備えられるか
金利タイプを選ぶ際は、家計にゆとりがあるかどうかを見極めましょう。変動金利は金利が上がると返済額も増えます。毎月の支出に余裕があれば、将来の金利上昇にも対応しやすくなります。
逆に、収支がギリギリだと、少しの返済増でも生活が圧迫されるおそれがあります。固定金利なら一定額の返済で安心ですが、初期の負担はやや重めです。将来の支出や収入の変化も考え、自分に合った返済スタイルを選ぶことが大切です。
将来の金利上昇リスクへの備えはあるか
将来の金利上昇に備える視点は、金利タイプ選びで後悔しないために重要です。変動金利は今は低めでも、上昇すれば返済額が増えます。その変化に家計が耐えられるか、事前に試算しておきましょう。
金利が一定のタイプを選べば、途中で上がっても影響は受けません。ただし月々の返済額はやや高くなりがちです。自分の家計や将来設計に合わせ、金利が上がったときの備えがあるかを考えてから選びましょう。
「安心重視」「低コスト重視」のどちらを重視するか
「安心重視」か「低コスト重視」か、どちらを優先するかをはっきりさせましょう。返済額が変わらない安心感を求めるなら、固定金利が合うかもしれません。
一方、少しでも毎月の負担を軽くしたいなら、変動金利のほうが魅力に感じる人もいます。ただし、将来の金利が上がる可能性もあるため、自分の収入や家計の余裕も考えて選ぶことが大切です。焦って決めず、金銭面を考慮したり家族と話し合ったりしたうえで、自分たちに合ったタイプを選ぶとよいでしょう。
変動金利のリスクと現実|親世代との違いとは
金利タイプのなかでも変動金利は、景気の影響などで金利が変動するリスクがあります。過去と現在の金利状況がどのように変化しているのか解説します。また、金利が変動する理由やリスクを抑える対策も解説しているので参考にしてみてください。
- 昔の「金利爆上げ時代」と今の金利環境を比較
- 金利が変動する主な要因とは
- リスクを抑える3つの対策
昔の「金利爆上げ時代」と今の金利環境を比較
親世代が経験した1990年代は、変動金利が年6%を超えることもあり、返済額が大幅に増えた例がありました。今は日銀の政策で低金利が続いていますが、将来も安心とは限りません。
金利が上がれば家計への影響も出るため、余裕ある返済計画が重要です。今の低金利だけを見て決めると、環境が変わった時に慌てる可能性もあります。親世代との違いを知ったうえで、慎重に判断する必要があります。
金利が変動する主な要因とは
変動金利は景気や物価、日銀の金融政策に左右されます。景気が良くなると物価が上がりやすく、金利も上昇する傾向があります。逆に景気が悪くなれば金利は下がることが多いです。
住宅ローンの金利は、こうした状況を受けて銀行が決定しています。今は金利が低くても、将来も続く保証はありません。返済額が増える可能性を考え、無理のない計画を立てることが重要です。
リスクを抑える3つの対策
変動金利は上昇すると返済額が増える可能性がありますが、対策次第でリスクを軽減できます。例えば、「短期間での完済を目指す」ことで、金利が上がる前に完済できるかもしれません。また「毎月の返済に余裕を持たせ、急な支出にも対応できる資金を確保しておく」と安心です。
さらに「定期的に金利動向を確認し、固定型への変更も視野に入れる」と、環境変化に柔軟に対応しやすくなります。かつてのような高金利時代とは異なりますが、今も計画的な返済姿勢が重要です。
zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし
\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

安心できる住宅予算の出し方とは?
住宅購入で何より大切なのは、住宅ローンの重圧から自由になる「資金計画」です。オンラインセミナー「小さいリスクで家を買う方法」では、お金の専門家による「安心予算」の算出方法を公開。
家を買うことは豊かな人生のための手段です。無理なく家を購入し、その後の暮らしも楽しみませんか?
金利差でどれだけ支払い額が変わる?シミュレーションで解説
金利差があると、実際の支払額がどれくらい変わるのかシミュレーションで解説します。多少の金利差でも総支払額に大きく影響することを理解しておきましょう。
- 金利が0.5%違うと総額でどれくらい差が出る?
- 借入額や返済年数が増えると差はどう広がる?
金利が0.5%違うと総額でどれくらい差が出る?
金利差はわずかでも、返済総額に大きな影響を与えます。例えば、3,000万円を35年ローンで借りた場合、金利1.0%なら月約8万5千円、1.5%なら約9万2千円。月々の差は約7千円ですが、35年で約300万円もの差になります。
住宅ローンは長期の支払いになるため、金利は軽視できません。金融機関を選ぶ際は、金利の数字だけでなく返済総額も必ず確認しましょう。
借入額や返済年数が増えると差はどう広がる?
金利差はわずかでも、借入額や返済年数が大きいと、総返済額の差も大きくなります。例えば、3,000万円を35年で借りると、金利1.0%と1.5%では総額に約280万円の差が出ます。月々の返済でも約6,800円ほど変わります。借入額が4,000万円になると、その差は約370万円に広がります。
また、3,000万円でも返済年数を25年に短くすると、同じ金利差でも総返済額の差は約220万円程度に縮まります。金利の数字だけでなく、借入額と期間に応じて総返済額を比較することが大切です。複数のシミュレーションを行い、自分に合った選択をしましょう。
住宅ローン金利の仕組みに関するよくある質問
住宅ローン金利の仕組みに関するよくある質問をご紹介します。金利に対する疑問や不安を参考にしてみましょう。
- 変動金利の「5年ルール」「125%ルール」とは?
- 借り換えで金利が下がれば本当に得になる?注意点は?
- 変動金利は今後どのように推移する?
変動金利の「5年ルール」「125%ルール」とは?
変動金利を選ぶなら、「5年ルール」と「125%ルール」は押さえておきましょう。「5年ルール」は、原則として返済額が5年間は見直されない仕組みです。ただし、急激な金利変動時には例外もあります。
「125%ルール」は、6年目以降に返済額が見直される場合でも、前回返済額の1.25倍が上限となる目安です。どちらも急な負担増を防ぐ工夫ですが、利息が増えると返済期間が延びるリスクもあるため、ルールを理解したうえで返済計画を立てましょう。
借り換えで金利が下がれば本当に得になる?注意点は?
金利が下がれば毎月の返済額も減り、家計に余裕が生まれやすくなります。ただし、得になるかは「手数料」と「残りの返済期間」に左右されます。
手数料が高いと、せっかくの金利差が帳消しになる可能性もあります。返済期間が短いと差額も小さくなりがちです。一般的に金利差が0.3~0.5%以上あり、返済が10年以上残っていればメリットが出やすい傾向があります。借り換えは一度きりでなく、将来的に再検討も可能です。目先の利率だけでなく、総支払額で比較して判断しましょう。
変動金利は今後どのように推移する?
現在は歴史的な低金利が続いていますが、2024年に長期金利が上昇した影響もあり、今後は徐々に見直される可能性があります。日銀が金融緩和から引き締めに転じれば、金融機関の住宅ローン金利にも影響します。
2025年以降も急激な上昇は考えにくいものの、物価や景気の動向次第で少しずつ上がるリスクがあります。今は金利が低くても、将来の上昇に備えて返済額に余裕を持つことが大切です。変動金利を選ぶ場合は、金利が上がったときの影響を事前に確認しておきましょう。
まとめ:住宅ローン金利の仕組みを理解して無理のない返済をしよう!
住宅ローン金利の意味や仕組み、金利タイプや返済時の注意点などを解説しました。
住宅ローンの金利とは、借入額に対する利息であり、借入額や利率により総返済額が大きく変動します。0.1%の違いであっても、長期間の返済となれば、数百万円の差になるケースも少なくありません。また、変動金利を選択した場合、将来的に金利が上昇する可能性もあるため、今以上に返済額が増えるおそれもあります。
住宅ローンの利用を検討している方、住宅ローンを組んでいて返済にお困りの方は、ぜひこの記事を参考にして住宅ローンの利用や借り換えを検討してみましょう。