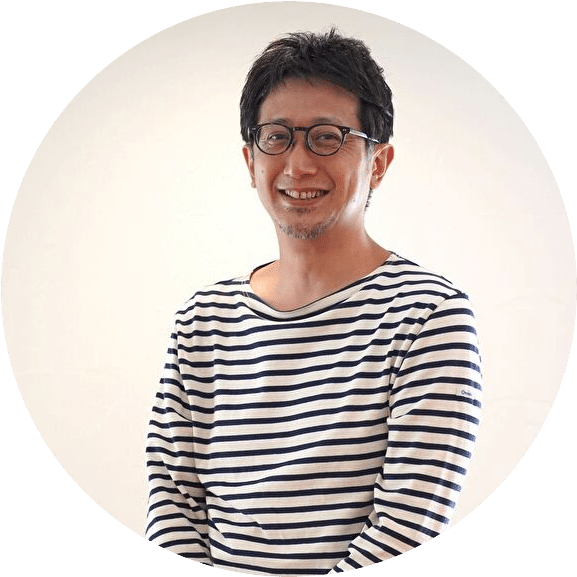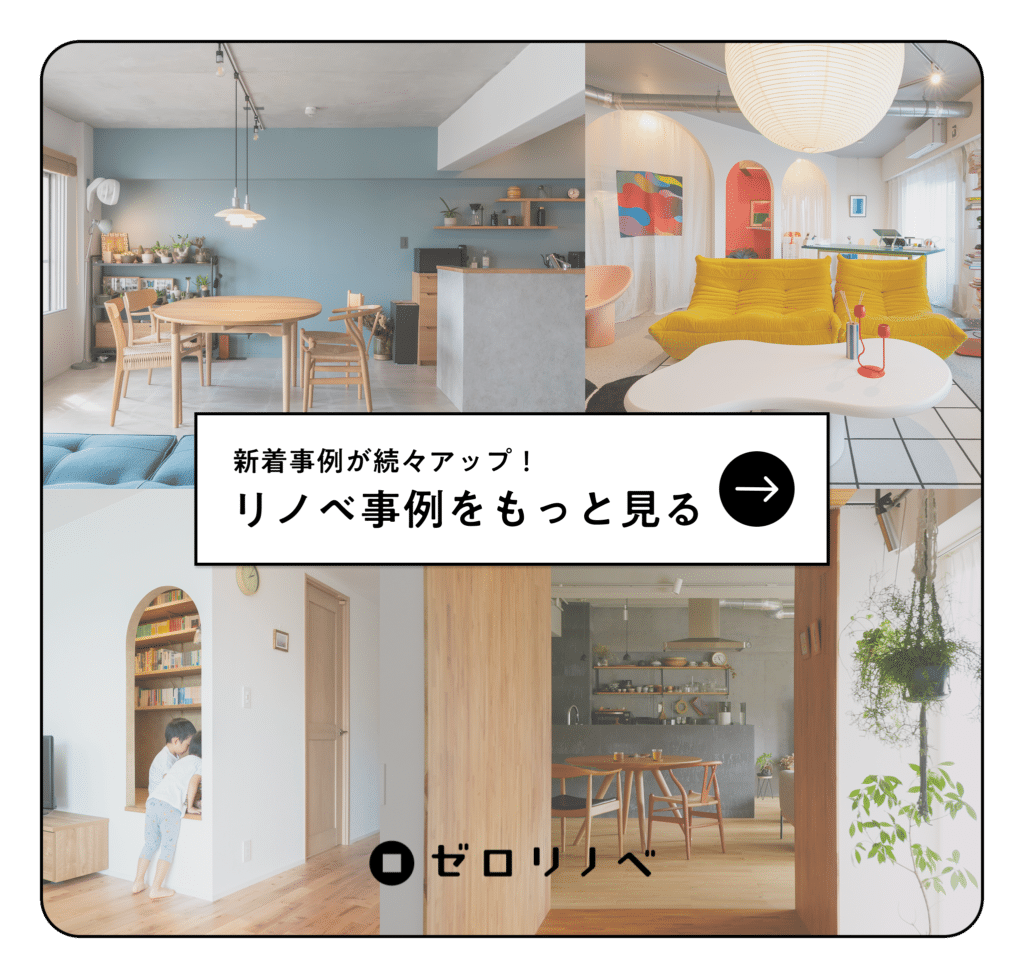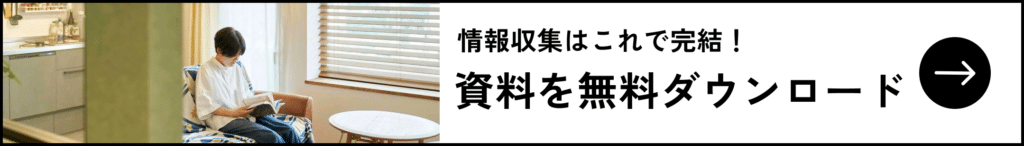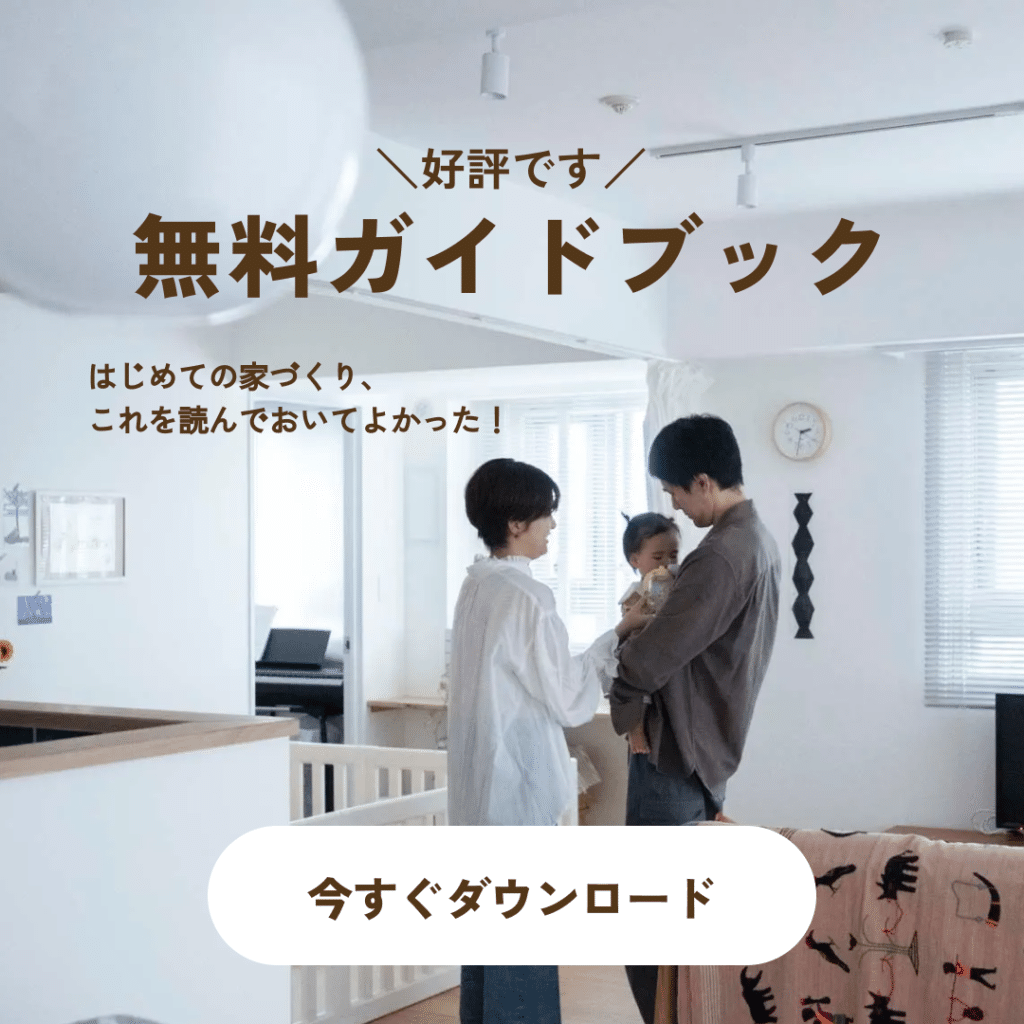引っ越し時の市役所手続き完全ガイド:スムーズに済ませる5つの必須ステップ

引っ越し時に必要な市役所(区役所・町村役場)での手続きを、転居・転出入別に詳しく解説します。転居届・転出届・転入届の提出方法や必要書類、法定期限、マイナンバーカードの住所変更、印鑑登録、国民健康保険など関連手続きまで、忘れがちな項目もチェックリスト形式で網羅。過料を避け、スムーズに新生活を始めるための完全ガイドです。


\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/
引っ越しパターン別に異なる市役所手続き:まずは自分のケースを確認
引っ越し時に市役所(区役所・町村役場)で行う手続きは、引っ越しのパターンによって大きく異なります。同一市区町村内での引っ越し(例:東京都新宿区内での引っ越し)の場合は「転居届」の提出が必要です。一方、他の市区町村への引っ越し(例:東京都新宿区から横浜市へ)の場合は、旧住所地での「転出届」と新住所地での「転入届」の両方の手続きが必要となります。これらの手続きは法律で定められており、引っ越し後14日以内という期限があるため、計画的に進めることが重要です。1)2)3)
市役所での手続きは、住民基本台帳法に基づく法的義務です。期限内に手続きを行わない場合、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。また、これらの基本的な住所変更手続きに加えて、マイナンバーカードの住所変更、印鑑登録、国民健康保険、国民年金、介護保険などの関連手続きも必要になることがあります。これらの手続きを忘れると、行政サービスを適切に受けられなくなる可能性があるため、チェックリストを作成して漏れがないようにすることをおすすめします。この記事では、引っ越しパターン別に必要な手続きと、スムーズに進めるためのポイントを詳しく解説します。1)2)3)4)
同一市区町村内での引っ越し:転居届の提出方法と注意点
同一市区町村内での引っ越し(例えば、同じ市内で住所が変わる場合)は「転居」と呼ばれ、この場合に必要な手続きは「転居届」の提出です。転居届は、引っ越し日から14日以内に、現在住んでいる市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)で手続きを行う必要があります。この期限は住民基本台帳法で定められた法定期限であり、これを過ぎると過料(罰金)が科される可能性があるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。1)2)3)
転居届の提出に必要なものは、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と印鑑です。また、国民健康保険に加入している場合は保険証も持参するとスムーズです。転居届の提出は、本人または世帯主、同一世帯の人が手続きできます。代理人による申請も可能ですが、その場合は委任状が必要になることが多いです。また、郵送やオンラインでの手続きは自治体によって対応が異なり、多くの場合は役所窓口での手続きが基本となります。引っ越し前に各自治体の公式ウェブサイトで確認するか、直接窓口に問い合わせて、必要書類や手続き方法を確認しておくことをおすすめします。1)2)3)
オンラインでの転居届提出:マイナンバーカードを活用した便利な方法
近年、マイナンバーカードの普及に伴い、一部の市区町村ではオンラインでの転居届提出が可能になっています。マイナンバーカードを持っている場合、「マイナポータル」や「引越れんらく帳」などのサービスを利用して、一部の手続きをオンラインで進めることができます。これにより、役所の窓口に行く時間を節約できるというメリットがあります。3)
オンラインで転居届を提出する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。また、マイナポータルへのログインには事前にユーザー登録が必要となります。ただし、現時点ではすべての自治体がオンライン手続きに対応しているわけではなく、また手続きの一部のみがオンライン化されているケースもあります。実際にどの程度オンラインで手続きが完結するかは、住んでいる自治体の対応状況によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。オンライン手続きが利用できる場合でも、一部の手続きは窓口での対応が必要になることがあるため、その点も注意が必要です。3)
他市区町村への引っ越し:転出届と転入届の手続き順序
他の市区町村への引っ越し(例:東京都新宿区から横浜市へ)の場合は、「転出」と「転入」の両方の手続きが必要です。まず、旧住所地の市区町村役所で「転出届」を提出し、次に新住所地の市区町村役所で「転入届」を提出します。これらの手続きには期限があり、適切なタイミングで行うことが重要です。2)3)
転出届は、引っ越しの14日前から当日までに旧住所地の市区町村役所で提出します。必要書類は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録している場合)などです。転出届を提出すると「転出証明書」が発行されます。この転出証明書は、新住所地での転入届提出時に必要となる重要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。2)3)
転入届は、引っ越し後14日以内に新住所地の市区町村役所で提出します。必要書類は、転出証明書、本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード(持っている場合)などです。転入届の提出も本人または世帯主、同一世帯の人が行うのが基本ですが、代理人による手続きも可能です(ただし委任状が必要)。転入届の提出が完了すると、住民票が新住所に移動し、選挙権の行使や各種行政サービスの利用が可能になります。3)4)
世帯分離・世帯合併を伴う場合の注意点
引っ越しと同時に世帯構成が変わる場合(例:子どもが独立して別世帯になる、結婚して世帯を合わせるなど)は、「世帯分離」や「世帯合併」の手続きも必要になることがあります。これらの手続きは転居届や転入届と同時に行うことができますが、追加の書類や確認事項が必要となる場合があります。
世帯分離の場合は、分離される人の同意が必要です。また、世帯主が変わる場合は、新しい世帯主の申請も必要となります。世帯合併の場合は、合併する両方の世帯の同意が必要です。これらの手続きを行う際は、本人確認書類や世帯全員の関係性を証明する書類(戸籍謄本など)が求められることがあります。
また、世帯構成が変わることで、国民健康保険や国民年金、介護保険、児童手当などの各種手当や福祉サービスの受給資格や金額が変わる可能性があります。そのため、世帯分離・世帯合併を伴う引っ越しの場合は、これらの関連手続きについても役所の担当窓口で相談し、必要な手続きを確認することをおすすめします。
その他の主な手続き:マイナンバーカードから健康保険まで
引っ越し時には、転居届・転出届・転入届の基本的な住所変更手続きに加えて、その他にも様々な関連手続きが必要になることがあります。特に重要なのが、マイナンバーカードの住所変更、印鑑登録の変更または新規登録、国民健康保険・国民年金・介護保険の住所変更手続きです。また、お子さんがいる家庭では児童手当や子どもの転校・転園手続きも必要になります。これらの手続きは、できるだけ転居届・転入届と同時に行うと効率的です。1)3)
これらの関連手続きを忘れると、行政サービスを適切に受けられなくなる可能性があります。例えば、マイナンバーカードの住所変更を行わないと、転入届提出後90日を経過した場合にカードが失効してしまいます。また、国民健康保険の住所変更を行わないと、医療機関での保険適用に問題が生じる可能性があります。印鑑登録も、公的な書類や契約書に使用する印鑑証明書の取得に必要となります。これらの手続きを漏れなく行うためには、チェックリストを作成して計画的に進めることをおすすめします。このセクションでは、それぞれの手続きの詳細と注意点を解説します。1)3)
マイナンバーカードの住所変更:期限と手続き方法
マイナンバーカードを持っている場合、引っ越し後はカードの住所変更手続きが必要です。この手続きは転入届提出後90日以内に行わなければなりません。期限を過ぎるとマイナンバーカードが失効し、再発行手続きが必要になるため注意が必要です。マイナンバーカードの住所変更は、転入届または転居届の提出と同時に行うことができます。3)
マイナンバーカードの住所変更手続きに必要なものは、マイナンバーカード本体と本人確認書類です。手続きは原則として本人が行う必要がありますが、やむを得ない理由がある場合は代理人による手続きも可能です(ただし委任状が必要)。住所変更手続きが完了すると、カードの裏面に新しい住所が記載されます。マイナンバーカードは本人確認書類として広く利用されるようになっているため、引っ越し後はできるだけ早く住所変更手続きを行うことをおすすめします。3)
なお、マイナンバーカードの電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)も住所変更に伴い更新が必要となります。電子証明書の更新も住所変更手続きと同時に行うことができます。電子証明書はマイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得、e-Taxでの確定申告など、様々な電子手続きで利用されるため、忘れずに更新しておきましょう。3)
印鑑登録の変更または新規登録:各種証明書取得のために
印鑑登録は、公的な書類や契約書に使用する印鑑証明書を取得するために必要な手続きです。引っ越しに伴い、印鑑登録の変更または新規登録が必要になることがあります。同一市区町村内での引っ越し(転居)の場合は印鑑登録の住所変更が必要です。他市区町村への引っ越し(転出・転入)の場合は、前住所地での印鑑登録は自動的に廃止されるため、新住所地で改めて新規登録する必要があります。1)3)
印鑑登録の手続きに必要なものは、登録する印鑑と本人確認書類です。本人確認書類としては、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが利用できます。印鑑登録は原則として本人が行う必要がありますが、代理人による申請も可能です(ただし委任状と代理人の本人確認書類が必要)。登録が完了すると「印鑑登録証」(カード形式の場合が多い)が発行されます。この印鑑登録証は印鑑証明書を取得する際に必要となるため、大切に保管しましょう。1)3)
なお、印鑑登録ができる印鑑には一定の基準があります。一般的に、プラスチック製の印鑑やゴム印、誰でも簡単に入手できる既製品の印鑑は登録できない場合があります。また、同一世帯内で同じ印鑑を重複して登録することもできません。印鑑登録の詳細な基準は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。1)3)
国民健康保険・国民年金・介護保険の手続き:保険サービス継続のために
国民健康保険、国民年金、介護保険などの社会保険関連の手続きも、引っ越し時には忘れずに行う必要があります。これらの手続きは通常、転居届または転入届の提出と同時に行うことができます。1)3)
国民健康保険の手続き 国民健康保険に加入している場合、引っ越しに伴い住所変更の手続きが必要です。同一市区町村内での引っ越し(転居)の場合は住所変更のみ、他市区町村への引っ越し(転出・転入)の場合は脱退と加入の手続きが必要です。手続きに必要なものは、国民健康保険証、本人確認書類、印鑑などです。手続きが完了すると、新しい保険証が発行されます。なお、会社の健康保険に加入している場合は、勤務先を通じて住所変更の手続きを行います。1)3)
国民年金の手続き 国民年金第1号被保険者(自営業者・学生・無職の人など)の場合、引っ越しに伴い住所変更の手続きが必要です。手続きに必要なものは、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、本人確認書類、印鑑などです。国民年金第2号被保険者(会社員・公務員など)や第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の場合は、勤務先または配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。2)3)
介護保険の手続き 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人、または65歳以上の人は介護保険の被保険者となり、引っ越しに伴い住所変更の手続きが必要です。同一市区町村内での引っ越し(転居)の場合は住所変更のみ、他市区町村への引っ越し(転出・転入)の場合は脱退と加入の手続きが必要です。手続きに必要なものは、介護保険証(持っている場合)、本人確認書類、印鑑などです。1)3)
これらの社会保険関連の手続きを忘れると、医療機関での保険適用や年金の受給に問題が生じる可能性があるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。


\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/
手続きの期限と注意点:過料を避けるために知っておくべきこと
引っ越し時の市役所での各種手続きには、法律で定められた期限があります。特に重要なのが「引っ越し日から14日以内」という転居届・転入届の提出期限です。この期限を過ぎると住民基本台帳法に基づき、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。実際には即座に罰則が適用されるケースは少ないですが、手続きが大幅に遅れると厳しく対応されることもあるため、必ず期限内に手続きを行うようにしましょう。2)3)
また、マイナンバーカードの住所変更にも「転入届提出後90日以内」という期限があり、これを過ぎるとカードが失効してしまいます。その他の手続きにも様々な期限や注意点があるため、計画的に進めることが重要です。特に役所の窓口は平日の開庁時間内(通常は8:30〜17:15頃)しか開いていないことが多いため、仕事や学校がある方は時間の調整が必要です。自治体によっては一部の窓口が延長営業や休日開庁をしている場合もありますので、事前に確認するとよいでしょう。2)3)4)
なお、必要書類や手続き方法は自治体によって異なる場合があります。特に転入届の提出時に必要な書類や、印鑑登録の条件などは自治体ごとに細かな違いがあるため、引っ越し先の市区町村の公式ウェブサイトや窓口で事前に確認しておくことをおすすめします。このセクションでは、手続きの期限や注意点について詳しく解説します。2)3)4)
期限を過ぎた場合の対応:遅延理由と必要な対応
引っ越し後14日以内という転居届・転入届の提出期限を過ぎてしまった場合でも、なるべく早く手続きを行うことが重要です。期限を過ぎた場合は、窓口で遅延理由を説明する必要があります。やむを得ない理由(病気や入院、海外滞在など)があれば、その事情を説明し、可能であれば証明できる書類を提示するとよいでしょう。2)3)
期限を大幅に過ぎた場合でも、基本的には通常の手続きと同じ流れで進められます。ただし、過料(罰金)が科される可能性があることは念頭に置いておきましょう。また、期限を過ぎたことで関連する手続き(マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険の加入など)にも影響が出る可能性があります。特にマイナンバーカードは転入届提出後90日を過ぎると失効してしまうため、再発行手続きが必要になります。2)3)
なお、期限内に手続きを行うのが難しい特別な事情がある場合(例:長期入院や海外赴任など)は、事前に役所に相談しておくことをおすすめします。場合によっては、特例的な対応が可能なケースもあります。いずれにせよ、手続きが遅れそうな場合は、できるだけ早く役所に連絡し、適切な対応方法を相談することが大切です。2)3)
マイナポータル・引越れんらく帳を活用したオンライン手続き
近年、引っ越し手続きの一部をオンラインで行えるサービスが拡充されています。特に「マイナポータル」や「引越れんらく帳」を利用したオンライン手続きは、窓口での待ち時間削減や手続きの効率化に役立ちます。ただし、すべての手続きをオンラインで完結できるわけではなく、多くの場合は一部の事前申請のみがオンラインで可能となっています。3)
マイナポータルを利用したオンライン手続きには、マイナンバーカードとICカードリーダーまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。また、事前にマイナポータルのアカウント登録が必要となります。引越れんらく帳は、引っ越しに関連する複数の手続き(市区町村への届出、電気・ガス・水道などの住所変更)をまとめて行えるサービスです。これらのサービスを利用する場合も、最終的には窓口での本人確認や書類提出が必要になることが多いため、完全にオンラインで手続きが完結するわけではありません。3)
オンライン手続きの対応状況は自治体によって異なります。特に小規模な自治体ではまだ対応していないケースもあります。利用を検討する場合は、事前に各自治体の公式ウェブサイトで確認するか、直接窓口に問い合わせることをおすすめします。オンライン手続きが利用できる場合でも、初回は操作方法や必要な準備に戸惑うこともあるため、余裕をもって対応することが大切です。3)
FAQ:引っ越し時の市役所手続きに関するよくある質問
引っ越し時の市役所手続きについて、多くの方が疑問や不安を感じています。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、スムーズな引っ越し手続きを進めてください。
引越し時に必要な書類はどこで確認できる?
引っ越し時に必要な書類は、基本的に引っ越し先(転入先)または現在住んでいる市区町村(転出元/転居元)の公式ウェブサイトで確認できます。多くの自治体では、「転入届」「転出届」「転居届」のページを設けており、必要書類や手続き方法を詳しく説明しています。また、直接役所の窓口に電話で問い合わせることもできます。
一般的に必要な書類としては、以下のようなものがあります:
転出届の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
転入届の場合
- 転出証明書
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバーカード(持っている場合)
転居届の場合
- 本人確認書類
- 印鑑
ただし、これらは基本的な書類であり、世帯構成や各種制度への加入状況によって、追加の書類が必要になる場合があります。例えば、児童手当を受給している場合は受給者証、介護保険を利用している場合は介護保険証なども必要になることがあります。事前に自治体の公式ウェブサイトで確認するか、直接窓口に問い合わせて、必要書類を漏れなく準備しましょう。2)3)4)
引越し前と引越し後の役所手続きの違いは?
引っ越し前と引っ越し後では、役所で行う手続きの種類や内容が異なります。主な違いは以下の通りです:
引っ越し前に行う手続き
- 転出届の提出(他市区町村へ引っ越す場合のみ)
- 引っ越しの14日前から当日までに旧住所地の役所で手続き
- 転出証明書を受け取る
引っ越し後に行う手続き
- 転入届の提出(他市区町村から引っ越してきた場合)
- 引っ越し後14日以内に新住所地の役所で手続き
- 転出証明書が必要
- 転居届の提出(同一市区町村内での引っ越しの場合)
- 引っ越し後14日以内に現在の市区町村の役所で手続き
- マイナンバーカードの住所変更
- 印鑑登録の変更または新規登録
- 国民健康保険・国民年金・介護保険の住所変更
- 児童手当、子どもの転校・転園手続き(該当者のみ)
このように、引っ越し前は主に転出届の提出が中心となりますが、引っ越し後は転入届または転居届の提出に加えて、様々な関連手続きが必要になります。特に引っ越し後の手続きは種類が多く、期限もあるため、計画的に進めることが重要です。引っ越し後の手続きは、できるだけまとめて行うと効率的です。例えば、転入届・転居届の提出と同時に、マイナンバーカードの住所変更や国民健康保険の手続きなども行うとよいでしょう。2)3)
引越し時に役所で行う手続きの期限は?
引っ越し時に役所で行う主な手続きの期限は以下の通りです:
転出届
- 引っ越しの14日前から当日までに旧住所地の役所で手続き
転入届・転居届
- 引っ越し後14日以内に新住所地または現在の市区町村の役所で手続き
- この期限は住民基本台帳法で定められた法定期限であり、過ぎると過料(罰金)が科される可能性あり
マイナンバーカードの住所変更
- 転入届提出後90日以内に手続き
- 期限を過ぎるとカードが失効し、再発行手続きが必要になる
国民健康保険・国民年金・介護保険の住所変更
- 明確な期限は設定されていないが、転入届・転居届と同時に行うのが望ましい
- 手続きが遅れると保険証の発行も遅れ、医療機関での保険適用に問題が生じる可能性あり
児童手当の住所変更
- 引っ越し後15日以内に手続きするのが望ましい
- 手続きが遅れると支給が一時停止される可能性あり
これらの期限を守ることで、行政サービスを滞りなく受け続けることができます。特に転入届・転居届の14日以内という期限は重要です。仕事や学校の都合で平日に役所に行くのが難しい場合は、休暇を取るか、一部の自治体で実施している休日開庁や窓口時間延長を利用するとよいでしょう。また、引っ越しシーズン(3〜4月)は窓口が混雑するため、余裕をもった計画を立てることをおすすめします。2)3)4)
引越し時にマイナンバーカードの更新は必要?
引っ越し時にはマイナンバーカードの「更新」ではなく「住所変更」の手続きが必要です。マイナンバー(個人番号)自体は引っ越しによって変わりませんが、カードに記載されている住所情報を更新する必要があります。この手続きは、転入届または転居届の提出と同時に行うことができます。3)
マイナンバーカードの住所変更手続きには、カード本体と本人確認書類が必要です。手続きは原則として本人が行う必要がありますが、やむを得ない理由がある場合は代理人による手続きも可能です(ただし委任状が必要)。住所変更手続きが完了すると、カードの裏面に新しい住所が記載されます。3)
重要な注意点として、マイナンバーカードの住所変更手続きには期限があります。他市区町村への引っ越し(転出・転入)の場合、転入届提出後90日以内に手続きを行わなければなりません。この期限を過ぎるとカードが失効し、再発行手続きが必要になります。再発行には時間と手間がかかるため、転入届と同時に住所変更手続きを行うことをおすすめします。3)
また、マイナンバーカードの電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)も住所変更に伴い更新が必要となります。電子証明書の更新も住所変更手続きと同時に行うことができます。電子証明書はマイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得、e-Taxでの確定申告など、様々な電子手続きで利用されるため、忘れずに更新しておきましょう。3)
引越し時に国民健康保険の加入手続きはどこで行う?
国民健康保険の加入手続きは、新住所地の市区町村役所(市役所・区役所・町村役場)の国民健康保険担当窓口で行います。この手続きは、転入届または転居届の提出と同時に行うことができます。なお、加入手続きが必要になるのは以下のようなケースです:
- 他市区町村からの引っ越しで、前住所地でも国民健康保険に加入していた場合
- 会社を退職して社会保険から国民健康保険に切り替える場合
- 扶養から外れて新たに国民健康保険に加入する場合
国民健康保険の加入手続きに必要なものは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、印鑑、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)です。また、会社を退職して加入する場合は、「資格喪失証明書」や「離職票」などの退職を証明する書類も必要となります。1)3)
同一市区町村内での引っ越し(転居)の場合は、国民健康保険の資格はそのまま継続されますが、住所変更の手続きは必要です。この場合も市区町村役所の国民健康保険担当窓口で手続きを行います。必要なものは、国民健康保険証、本人確認書類、印鑑などです。1)3)
なお、会社の健康保険や共済組合などに加入している場合(いわゆる社会保険加入者)は、市区町村役所での国民健康保険の手続きは不要です。この場合は、勤務先を通じて健康保険の住所変更手続きを行います。ただし、家族が国民健康保険に加入している場合は、その家族分の手続きは必要となりますので注意しましょう。1)3)
まとめ:円滑な引っ越しのための市役所手続きチェックリスト
引っ越し時の市役所手続きは、引っ越しのパターン(同一市区町村内か、他市区町村への移動か)によって大きく異なります。同一市区町村内での引っ越しの場合は「転居届」の提出、他市区町村への引っ越しの場合は「転出届」と「転入届」の提出が基本となります。これらの手続きには法定期限(14日以内)があり、期限を過ぎると過料(罰金)が科される可能性があるため、計画的に進めることが重要です。1)2)3)4)
また、基本的な住所変更手続きに加えて、マイナンバーカードの住所変更、印鑑登録の変更または新規登録、国民健康保険・国民年金・介護保険の住所変更手続きなど、様々な関連手続きも必要になります。これらの手続きを漏れなく行うためには、チェックリストを作成して管理することをおすすめします。特に転入届・転居届と同時に行える手続きはまとめて行うと効率的です。1)2)3)4)
引っ越し時の市役所手続きは、新生活をスムーズに始めるための重要なステップです。この記事で紹介した手続きの流れやポイントを参考に、計画的に準備を進めてください。必要書類や手続き方法は自治体によって異なる場合があるため、事前に各市区町村の公式ウェブサイトで確認するか、直接窓口に問い合わせることをおすすめします。適切な準備と計画によって、円滑な引っ越しと新生活のスタートを切りましょう。1)2)3)4)
引っ越し時の市役所手続きチェックリスト
以下のチェックリストを参考に、自分の状況に合わせた手続き計画を立てましょう:
同一市区町村内での引っ越し(転居)の場合
- □ 転居届の提出(引っ越し後14日以内)
- □ マイナンバーカードの住所変更(持っている場合)
- □ 印鑑登録の住所変更(登録している場合)
- □ 国民健康保険の住所変更(加入している場合)
- □ 国民年金の住所変更(第1号被保険者の場合)
- □ 介護保険の住所変更(該当者のみ)
- □ 児童手当の住所変更(該当者のみ)
- □ 子どもの転校・転園手続き(該当者のみ)
他市区町村への引っ越し(転出・転入)の場合
- □ 転出届の提出(引っ越しの14日前から当日まで)
- □ 転出証明書の受け取り
- □ 転入届の提出(引っ越し後14日以内)
- □ マイナンバーカードの住所変更(持っている場合)
- □ 印鑑登録の新規登録(必要な場合)
- □ 国民健康保険の加入手続き(加入する場合)
- □ 国民年金の住所変更(第1号被保険者の場合)
- □ 介護保険の加入手続き(該当者のみ)
- □ 児童手当の申請(該当者のみ)
- □ 子どもの転校・転園手続き(該当者のみ)
これらの手続きを計画的に進めることで、行政サービスを滞りなく受け続けることができます。特に法定期限のある手続きは優先的に行い、新生活をスムーズにスタートさせましょう。1)2)3)4)


\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/